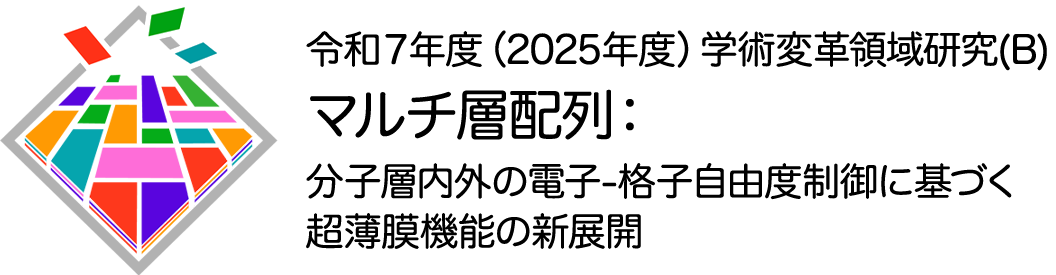領域概要
概要
物質の性質はその大きさや形状によって劇的に変化する。2次元原子層物質においては、3次元結晶では見られなかった特異な物理現象が次々と発見されており、現代科学における重要な研究領域となっている。これまでにない機能を持つ電子デバイスの創出に直結する可能性を持ち、新たな物質の開発への期待が高まっているが、主な研究対象は黒鉛の一層を取り出したグラフェンや無機物であった。
一方で、電子を受け取りやすい性質を持つアクセプター分子と電子を供与しやすい性質を持つドナー分子が規則的に並んだ電荷移動錯体と呼ばれる物質は、分子の組み合わせや配列を制御することによって、電気伝導性や磁性など多様な物性を示す。さらに、分子設計や外部からの刺激によって複数の電子相を柔軟に制御できるという特徴を有しており、3次元結晶の形態を対象として研究が進められてきた。
本研究では、電荷移動錯体を基盤物質として、電子をやり取りする複数の分子から構成される原子数個分の厚さ、すなわちナノメートルスケールの厚さの超薄膜の創製と、その物性の解明に取り組む。次元性を低下させることで、新たに生じる秩序構造、界面効果などにより、ナノスケール特有の新しい量子現象を探求する。分子設計の自由度を活かしたボトムアップ構築によって、分子を層内で2次元に並べた層内配列と、分子層を一層ずつ積層する層間配列を達成し、多種の分子が層配列した「マルチ層配列」超薄膜を創製する。この精密に制御された「マルチ層配列」構造は、従来にない結晶構造や電子状態を生み出し、薄膜特有の優れた外場応答性の発現や機能の創出へと繋がる。通常は極低温・高圧下でしか現れないエキゾチックな電子相を、常温・常圧で実現することを目指す。これにより、新しい原理に基づいた電子デバイスの開発へと繋がる道筋を切り拓く。

グラフェンなどに代表される多くの2次元原子層物質では、層内が共有結合やイオン結合といった強い化学結合で形成されているのに対し、層間は弱いファンデルワールス力(分散力)で積層している。この構造的異方性により、積層面に沿った劈開が容易であり、3次元結晶から剥離することで単層や数層からなる高品質な超薄膜を得ることが可能である。 一方、多くの分子性結晶は、分子間の相互作用が主に弱いファンデルワールス力に支配され、外場に依存した多彩な電子相を示すが、 明確な層状構造を持たず、3次元的な結晶構造を形成することが多い。このため、特定の面で劈開することはあっても、構造を乱さずに、グラフェンのように原子レベルで均一な厚みを持つ超薄膜を剥離によって得ることは極めて困難である。電荷移動錯体を含む分子性物質において、高秩序な構造を持つ超薄膜を再現性良く合理的に作製する技術は未だ確立されておらず、高品質な超薄膜の創製と基礎学理の構築に向けた基盤技術の開発が喫緊の課題となっている。
本研究は、分子設計の自由度が高く電子相の多様性に富む電荷移動錯体に注目することで、この課題の克服を目指す。分子を精密に制御しながら配列させるボトムアップ合成法を駆使することで、分子性物質特有の多彩な電子構造を示す「マルチ層配列」超薄膜の創製に挑戦するものである。
電荷移動錯体からなる多種の分子層を逐次的に積層させ、階層構造が制御された多様な電子相を有する「マルチ層配列」超薄膜を創出し、層配列と電子物性の相関を明らかにする。

A01:分子設計・合成
藤野 智子(代表・横浜国大)、原口 祐哉(分担・東京農工大)、吉見 一慶(分担・東京大)
電荷移動錯体における分子配列や層間の相互作用をもとに、特異な電子構造を設計し、導出する分子を化学合成する。無機層状物質などとの異種界面の形成などを通じて、新しい電子構造と物性を創出する。
A02:層構造の構築
牧浦 理恵(代表・東北大学)
気液界面法を利用し、電荷移動錯体の精密なボトムアップ自己組織化によって、分子配列が高度に制御された超薄膜を創製する。分子配列や電荷分布などの構造情報と特異な電子物性との相関を解明する。
A03:機能開拓
東野 寿樹(代表・産総研)、井上 悟(分担・山形大)、藤田 健志(分担・東京大)
マルチ層配列された電荷移動錯体の示す多彩な電子相を、外部刺激(光、電場、機械的歪みなど)によって精密に制御する技術を確立する。3次元結晶では観測されない低次元物性や機能を開拓し、デバイス応用を展開する。